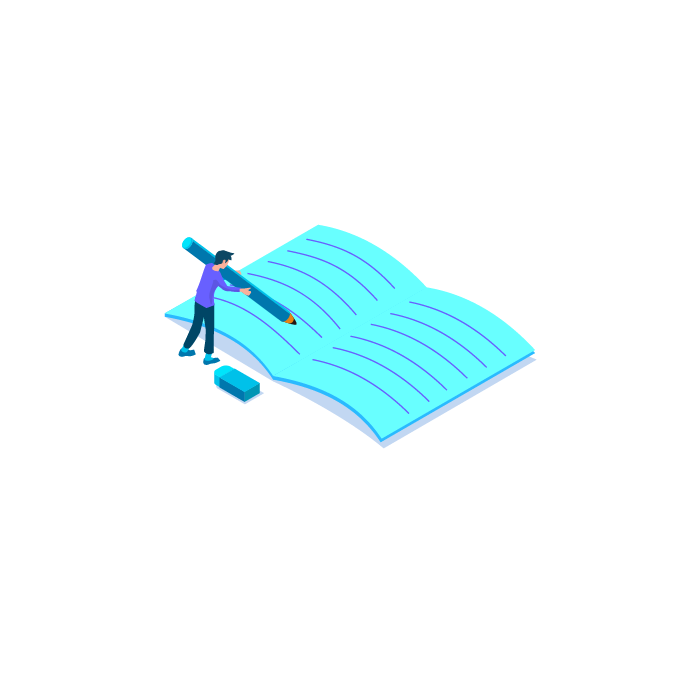皆さん「ランチェスター戦略」という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、こちらはビジネスにおける競争に勝つための理論と戦略を指します。イギリスの航空工学のエンジニアであるフレデリック・W・ランチェスターが発見した「ランチェスターの法則」を基に、日本で発展した販売戦略として体系化された考え方です。
簡単にランチェスター戦略のポイントを紹介すると、小規模企業やシェアが低い企業が市場で有利に展開するための戦略であり、弱者の戦略と強者の戦略の2種類が存在します。
そして弱者の戦略では、トップ企業のシェアが及んでいないニッチな客層や地域を選定したり、強者の戦略では、豊富な物量を確保して全国的なマスマーケットへ展開するといったポイントがあります。まさしく、地域産業である住宅事業に当てはまる基本戦略思考ではないでしょうか?
ここでいうランチェスター戦略での強者に当てはまる会社とは1000社中5社位しかなく、995社は競争条件が不利な会社になるという事で、ほとんどの会社は弱者の戦略で経営しなければならないということが書かれています。弱者とは、言い換えれば市場占有率が2位以下のことを指し、強者以外のすべてが弱者という解釈をしている点が面白い点です。
また、このランチェスター戦略の法則では「戦闘力=兵力の質?量」という法則が存在し、同じ武器なら勝敗は兵力数で決まるという定義をもとにした弱者の戦略と強者の戦略の2つに分けられているのがポイントです。
第1の法則は「一騎打ちの法則」とも呼ばれていて、第2法則は、近代兵器による遠隔戦やより広範な戦いを想定したものがあります。これを国内の住宅業界に当てはめて考察した場合、どのような具体的なアクションが見えてくるのかを皆さんと考えながら、紐解いていきたいと思います。
↓ ↓ メールマガジンの続きはこちらから ↓ ↓
ここで、第1法則と第2法則を比較すると、ハウスメーカーのような強者の損害は、第1法則を適用したときの方が影響は大きいので、地域工務店のような弱者はできるだけ強者を倒せるように、第1法則を適用できる場所で戦うべきということになります。
すなわち、わかりやすく表現するならば、狭い谷間のような場所に事業展開を進め、たとえ銃や大砲を強者が使用したとしても、一人で多数を攻撃不可能な状況にしながら、接近戦や1対1の戦闘にもっていけさえすれば、強者の損害を増やし、勝つことができるという訳です。ただ、この「狭い谷間」のいうキーワードこそが一体何であるかが、この戦略の一番重要な肝と言えるでしょう。
例えば、県下No.1の新築着工数を目指す会社は山のように存在しますが、地域でのメンテナンスを主軸に、点検物件数No.1を目指す会社はありませんし、設計段階での高い省エネスペックを目指す会社は沢山ありますが、完工時の高い施工品質を目指す会社は非常に少ないと言えます。
まず弱者である地域工務店こそ、何で1位になるかの強い願望と熱意が必要となり、この明確な目標がなければ、そもそもランチェスター戦略は成立しないのです。そして自社よりも大きな会社ばかりを攻撃目標にせず、強い会社と全く違う経営戦略で、独自にアクションしていくことが大切です。
もちろん第1法則において、多数であるほうが優勢であるのは間違いないので、その場合、敵を分散させ、如何に各個で撃破していく環境下を作れるかもポイントと言えるでしょう。
これからは、1位作りの目標対象を出来るだけ細分化し、自らが発見することが重要です。弱者は無理なく、まずは市場規模が小さな商品やサービスで1位になることを目指す事が懸命であり、出来るだけ商品の幅を狭くし、経営力の分散を防ぐことも経営的思考の1つです。
昨今、ショップ運営や福祉、または様々な多角的経営を試みる地域工務店も多く見かけますが、経営戦略的には一見新たなビジネスチャンスと解釈しがちですが、経営分散という原則からは成功する割合は非常に少ないように思います。是非、市場規模が小さな地域からでも1位になることの、選択と集中を意識してみてください。
次に弱者のマーケティング戦略ですが、営業地域の最大範囲を出来るだけ狭くする事です。むしろ市場規模が小さな業界や客層で1位になることを意識し、そこで1位になれるだけの戦術力を投入していく事が最優先となります。間接販売を避け、最終利用者へ直接販売することを重視しながら、お客様に感謝の心を直接伝えられる環境と力を高めていく事を忘れてはなりません。
また経営管理では、このようなローカル環境に適した人の力を集約し、より有効に発揮できるシンプルな組織やシステムを作ることです。つまり資金の固定化を防ぎながら、如何に経理の仕事を簡単にする事も重要となります。
これまでのように、私なりにランチェスター戦略を地域工務店事業の今後の展開に当てはめてきましたが、実は経営姿勢についても書かれおり、業界で継続的に成功している経営者は限られるため、弱者に当たる地域工務店の経営者こそ、朝型を中心に仕事を実践し、経営戦略の研究に力を入れながら上位3%に入る実力を身につけなければならないと示されています。小さな成功で調子に乗らず、生活内容を変えないという事も重要な経営姿勢の1つだと訴えています。
他社との経営交流会なども盛んな中、ついつい自社よりも一回り大きな会社を羨ましがったり、憧れの中から戦略を真似たり、背伸びする経営が増えているように思いますが、弱者全ての成したいゴールはきっと違う筈です。
是非、今月のコラムが今後の経営戦略での新たな気付きや後押しになれば幸いに思います。